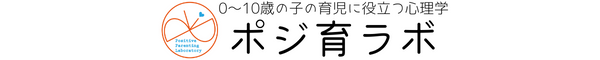子どものウソのトリセツ③~ウソを学習させないために
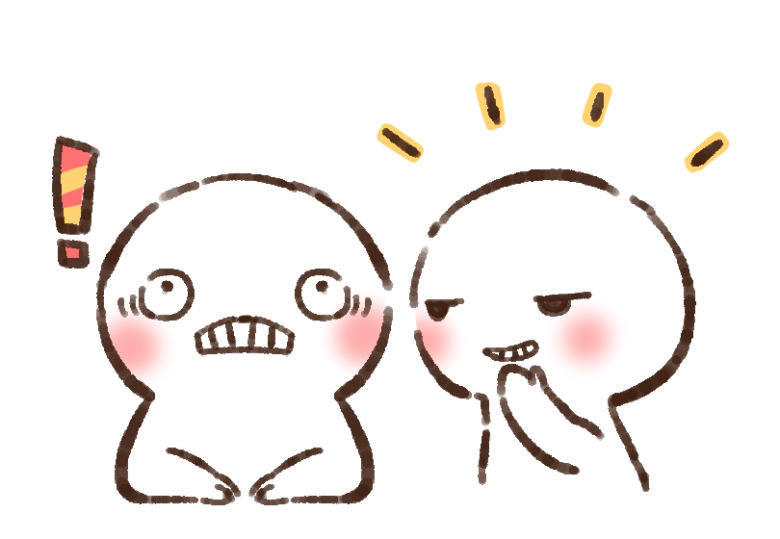
子どものウソのトリセツ①やトリセツ②では、幼少期に見られるウソの心理的背景や特徴、減らすための対策について触れました。
今回はトリセツ③。ウソは学習要素が強く、触れる頻度が多いとクセになりやすいことが知られていますが、実は親がそれに加担してしまっていることがあります。子どもに「ウソはダメ」と教えている以上、親もテキトーなことは言ってはいけない。今回はこんな内容をお伝えしていきます。
知らず知らずのうちに親もウソをついている?
子どもには「ウソはダメ」と教えていても、自分ではこんな言葉を口にしていませんか?
- 「片づけないなら、おもちゃは全部捨てちゃうよ」
- 「歯を磨かないなら、おやつはもうあげない!」
- 「宿題が終わらなければ、遊園地には行かないよ」
- 「言うことを聞かないなら、うちの子じゃないよ」
「つい言っちゃう」という人も多いのでは?でもそのあと、どう対応しましたか?
- 「本当は捨ててないし…」
- 「おやつ、あげちゃったし…」
- 「結局、遊園地には行ったし…」
- 「うちの子じゃないなんて、言うだけだし…」
このような言動の不一致を見た子どもは何を学ぶでしょうか?
- 「ママ、言ってることと違う…」
- 「パパの言葉は本気じゃないんだ」
- 「言うこととやることが違うな」
と気づく子もいるでしょう。
子どもが「ボク・ワタシやっていない」と言うと「この子はウソをついた!」と即座にリアクションするにもかかわらず、自分側の不一致は見逃してしまう……。子どもに「ウソはダメ」と教える以上、自らも「事実と矛盾することを言うのはよくない」と認識していくのは大事なことです。
脅しの効果は限定的
親がこうした大げさな発言をするのは、強い言葉の方が子どもが従うと期待するからです。「全部捨てる」と言えば驚いて片づけるだろうと。しかし、実行しなければ効果はありません。むしろ、数回で「ママ・パパはああ言ってもどうせやらない」と気づき、言っても聞かない悪循環に陥ります。まさにオオカミ少年状態なのです。「うちの子、何度言っても言うことを聞かない」と悩むことは多いですが、親自ら、自分の言葉の”重み”を薄めてしまってはもったいないですよね。
そして怖いのは、子どもはそれを真似するということ。「言うけど、やらない」を繰り返すと、子どもも同じように、空返事やごまかしを覚えるようになってしまいます。
実行可能な約束だけをする
解決策は、自分が実現できることだけを伝えることです。
避けるべき非現実的な表現:
- 「全部捨てちゃうよ」
- 「絶対に何も買ってあげない」
- 「もうどこにも連れて行かない」
代わりに使うべき実行可能な表現:
- 「ママが明日まで預かるからね」
- 「明日のお買い物ではお菓子は買わないよ」
- 「明日の朝は公園に連れて行かないよ」
実行可能なことを言い、その約束を親の方が守ることで、子どもは「親は言ったことを守る人だ」と信頼を深め、結果として言うことも聞くようになっていきます。逆に言えば、びっくりするようなことを言って動かそうとするだけでは、子どもは言うことを聞きません。その言葉が「本当じゃない」「どうせウソだ」と知っているからです。「できることだけ言う」「できないことは言わない」と意識し、親が率先して子どもをウソから守り、健全な信頼関係を築いていきましょう。
まとめ:親も意外とウソをついているという認識を
子どもがウソをつき始める幼少期は、親の影響力が最も強い時期でもあります。「子は親の鏡」という言葉があるように、正直な子に育てるためには親自身が正直であることが大切です。今回は、知らず知らずのうちに子どもに「ウソ」と受け取られかねない親の行動について見てきましたがいかがだったでしょうか。
親は子どものウソに非常に敏感に反応しますが、自分も気づかぬうちに「事実と反すること」を言っているかもしれない。このことを意識的に振り返っていきたいものです。
これまでの研究でも分かっているように、ウソは学習要素が強いので、虚言に触れる機会を極力減らすことはとても大事なこと。「できることだけ言う」「できないことは言わない」——たったこれだけのシンプルなルールで、親は子どもに正直さを教えることができます。親子の信頼関係を大切に育てるためにも、まずは自分の言葉を見直してみましょう。