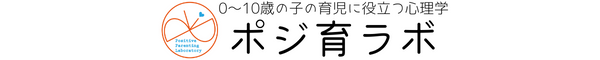上の子可愛くない症候群の対処法 | 専門家推奨7つのコツ

ここまでいくつかの記事で、「上の子可愛くない症候群」について触れてきました。この状態は子どもにとっても、親にとっても望ましい状態ではありませんので、できるだけ早く改善へと踏み出していきたいものです。ただ、これまでの相談事例を踏まえて言えることは、直接的に「可愛く思わなくちゃ」と思って改善するほど簡単ではないということです。かなりしっかりと分解、分析して改善の糸口を見つけていく必要があります。
そこで今回は、私のこれまでの経験を踏まえて、改善の糸口になることが多いものを項目ごとに取り上げていきます。
上の子可愛くない症候群の改善、解消は、大きく分けて3つの視点からアプローチできると考えています。
1. 環境の改革
2. 自分自身の改革
3. 子どもとの関係性の改革
それぞれの方法について具体的に見ていきましょう。
環境の改革
① 家事の負担を減らす
上の子を厳しい目で見てしまう背景に、日々の忙しさが関係していることは非常に多いと感じています。これは、上の子可愛くない症候群のみならず育児ストレス全般に言えることなので、時間のやりくりを工夫していくことは親業においてとても大切です。
その中でもっとも省略したり簡略化しやすいのは家事です。
• 家事の外部委託
• 家電のフル活用
• 家族や地域のサポート活用
• 完璧主義からの解放
がポイントになります。
ここで一番ネックになるのが、4つめの完璧主義からの解放だと感じています。「ちゃんとやりたい」という思いがあることで、「食器は手洗いしたい」「市販の食品は避けたい」「外部に委託するのは気が引ける」と1つめ、2つめ、3つめを実行しずらくしてしまっているのです。自分の“こだわり”は長年付き合っている相棒のような存在ですから、ポイと捨てられるものではありません。ただ、子どもへの愛情にまで影響を及ぼしている場合は、これを機に、「ちゃんと」を手放すことを真剣に考える必要があると思います。
1日24時間、できることしかできないと割り切り、簡略化できる家事はないかを探していきましょう。逆に育児の省略や簡略化は問題発生につながりやすいため、ここは省かずに、家事側で見つけていくようにします。
② ちゃんと機能するルールを作り直す
「上の子可愛くない症候群」は、子どもが言うことを聞かないことが要因になっている事例が多いと感じています。実際にカウンセリングで、「言うことを聞くようになったら愛情は戻る気がしますか?」と聞くと、多くの方が、「戻る気がする」「少なくとも改善するだろう」とおっしゃいます。
「子どもが全然言うことを聞かない!」と悩んでいるご家庭は、お家の中のルールや約束があいまいになっていることがとても多いです。名目上でのルールはあっても、ちっとも守られていない、そういう状況なので、常にイライラしてしまい、そこに時間を取られるので、愛情の薄れを感じやすくなっているのです。
よって、環境の改革の2つめは、ルールの見直しです。家庭を運営するには、親子でそこそこ守れるルールが必要です。厳しいルールでもなく、甘いルールでもなく、親も子も「まぁこれくらいなら」というところに線がある方が、地味にコツコツ続けられるので回転しやすくなり、結果的に愛情の回復につながるのです。
ルールがないお家の中に、新たなルールを作って実践するのはとても大変なことに感じるかもしれませんが、伸ばし伸ばしにしてしまうと、もっと改革が大変になります。「我が家は自由過ぎたのかもしれない」「ある程度言うことを聞いてくれたら見方が変わるかもしれない」こう思う方は、お家の中の仕組みづくりに着手することが、愛情回復への道筋になるはずです。自分で改革するにはどこから手を付けたらいいかわからないという方は、私の相談室でも並走できますのでお声をおかけください。
2.自分自身の改革
①誰かに気持ちを話してみる
自分の気持ちを誰かに話してみることも大切です。夫婦間で話せたら理想ですが、難しい場合は信頼できる友人や実家の家族に話してみるのも助けになることが多いです。ただ、悩みの性質上、「我が子を可愛く思えないなんて周りに相談できない」とおっしゃる方がかなりいるのも事実です。これが、悩みの抱え込みにつながってしまうのですが、そういう場合は、カウンセラーや育児相談窓口など、近くない第三者に話してみてほしいです。
言語化することで悩みの”かたまり”状態だったものが分解され、「ならば今何をしていったらいいのか」が見えやすくなります。あとみなさんがおっしゃるのは、「話すことで不思議なくらい気持ちが整理された」ということです。自分の頭の中だけに置いておくと、悩みはどんどんと渦を巻いていってしまい、悩みの根幹が見えにくくなってしまうことがよくありますが、人に話そうとすると、それを1つ1つひも解く必要があるので、改善に向けた方向性が見つかりやすいのです。
その会話自体が、「全否定していたけれど意外とできていることもある」「根っこでは子どもを大切に思っている」という気づきにつながることもよくあり、そこまで行けると、改善へのマインドセットを作りやすくなります。
② 本などで知識を増やす
上の子を可愛く思えない理由が、「言うことを聞かないから」「わがままで反抗的だから」などである場合、なぜそういう行動をとるのかを自分なりに分析してみることも有用です。その際に頼りにすべきは育児の知識です。とくに第一子の育児はだれにとっても初心者ですから、知識を補強することが助けになることは多々あります。本や雑誌、YouTubeなどから情報を集め、対策を立ててみるのも有効でしょう。
また、自分の怒りっぽいところを何とかしたいと感じているなら、アンガーマネジメントの知識をつけるのもおすすめです。
その際気をつけたいのは、どこから知識をもらうかです。今は情報があふれている時代なので、ネットで検索ワードを入れればたくさんの「ああしなさい」「こうしなさい」が出てきます。その中には双方が矛盾している知識もあったりします。だれでも情報を発信できる時代だからこそ、その知識の出どころが信頼のおける発信源かを見極める必要があります。
子育てにおいては、医療や体の発達に関しては小児科医、看護師、心の発達については公認心理師や臨床心理士、さらには子どもに触れることの多い保育士や助産師などの専門家がいます。信頼できる情報筋を見つけて、そこで学びを深めていけると一貫性のある知識が身につくはずです。
子育ては大変な仕事ですから、なんとなくの感覚でできるものではありません。知識が助けてくれる場面はたくさんありますので、目の前のことにやみくもに突進するのではなく、「今自分にどんな知識があったら助けになるか」を考えて、それに沿った補強をしていきましょう。
子どもとの関係性の改革
① 一緒の時間を過ごす
上の子可愛くない症候群で悩んでいるときは、子どもとの関係性が崩れていることが多いものです。もし子どもが「自分は愛されていない」「パパ/ママは自分のことが嫌いだ」のように気づいている場合はさらに状況は複雑化しています。今は気持ち的にやろうと思えることが少ないかもしれませんが、「上の子への愛情を改善したい」と思ったら、できるところから関わりを増やしていくことがとても重要です。理想形を目指すよりは、まずできるところからはじめていきましょう。
例:
• 子どもと一緒にテレビや動画を見る
• 2人でゲームをする
• ケーキを買ってきて一緒に食べる
• 子どもの好きなメニューを夕飯に出す
• 児童館などのイベントに一緒に行く など
「一緒に楽しむ」「一緒に喜ぶ」という体験を1日1回でもいいので作り、1回できたら2回、2回できたら3回……とペースを上げていけると望ましいです。このようなポジティブな関わりは、子どもが親に抱く愛着感情(アタッチメント)を強くしてくれます。このアタッチメントはその子の健全な心理発達に欠かせないものなので、意識的に機会を作っていきましょう。
② 声かけを変えてみる
問題が起きてからだと注意したり叱ったりするしかなくなってしまいますが、問題が起きる前だったら今のその状態をねぎらったり肯定したりすることができます。
上の子との関わりをできるだけ少なくしたいと思っている場合、どうしても問題が起きるまでそのままにしてしまうことが増えてしまいます。そうすると、上の子は「問題を起こせばパパ/ママはこっちを向いてくれる」と捉えやすく、さらに問題行動が増えることになってしまいます。
普通に過ごしている状態にも意識的に目を向けて、肯定的な言葉を伝えていきましょう。
例:
• 「もうここまで終わったんだね」と途中でもほめる
• 「ありがとう」「助かったよ」と感謝の気持ちを伝える
• 「がんばってるね」「自分を信じて」と勇気づける など
上の子が欲しているのは、このような「僕/私を見てくれている」という感覚です。べた褒めする必要はなく、ごく普通の日常に目線を配ることがポイントになるのでぜひ意識してみてください。
③上の子だからこそできる関わりを増やす
下の子にはまだ早いけれど、上の子ならもうできる。こんな形のコミュニケーションがあれば、上の子にとって特別感が得られやすいのでおすすめです。
例:
• 文字が読める子なら交換日記や手紙交換
• スマホを持っている子ならLineでコミュニケーション
• ハマっていることや「推し」の話
• 洋服やヘアスタイルなどのおしゃれに興味があれば、その話題 など
できそうなことから踏み込むことで、少しずつ関係性は変わっていくものです。「可愛いと思わなくちゃ」と思っても変わるものではないので、できることから着手しましょう。気持ちは後からついてきます。
まとめ
今回は上の子可愛くない症候群の対策についてお話をしてきました。上の子が愛されていない状態、さらには上の子がそれに気づいてしまっている状態は、長期化させてしまうと心に影響が出てきてしまいます。これを機に、ぜひ少しでもできるところから取りかかってみてください。
基本的な方向性は、
1. 環境の改革
2. 自分自身の改革
3. 子どもとの関係性の改革
です。
人それぞれ、どこに重きを置くかは変わってきますので、この3つについて、
1. 環境はどうか
2. 自分自身はどうか
3. 子どもとの関係性はどうか
と俯瞰し、より必要だと思うところを意識していってみてください。小さな積み重ねが、やがて大きな変化につながるはずです。